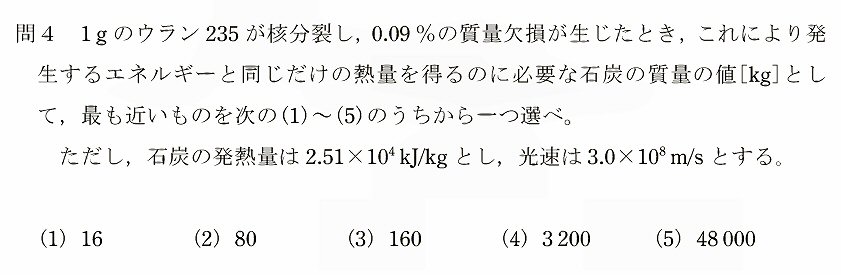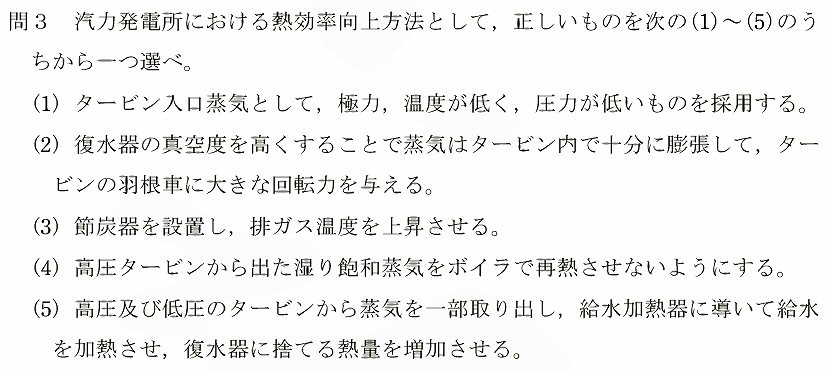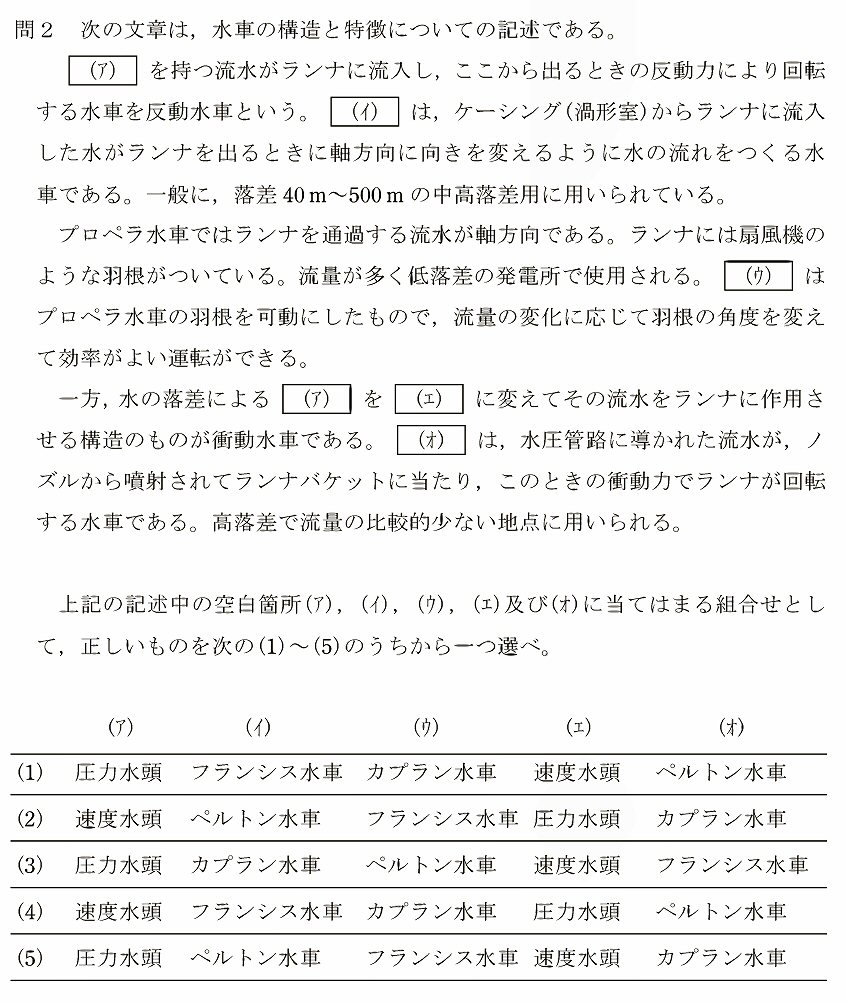前提
Ciscoの集中管理型アクセスポイントを二束三文で入手してきた。これを自律型に変更したい。
実機の状況
初期化などはせず、本当に外してきたままだった。
やりたいこと
集中管理型ファームウェアのap3g2-k9w8-*を、自律型のap3g-k9w7-*に入れ替える。
以下の説明において、192.168.a.bはAPのIPアドレス、192.168.a.cはTFTPサーバのIPアドレス、192.168.a.254はデフォゲのIPアドレスとする。(デフォゲの設定は不要のはずだけど、まぁ気分的にね)
作業
- ap3g2-k9w7-tar.153-3.JF12.tarとかを入手してくる。
- TFTPサーバを作り、上記ファイルにアクセスできるようにする。
- MODEボタンを押しっぱなしにして電源ON。
- ap: というカーソルで立ち上がるので、一旦電源を切って再起動
- Ciscoでログイン。デバッグモードにするため次のコマンドを入力
- #debug capwap console cli
- enableする。パスワードはCisco。そしてcapwapの設定を一旦リセットするために下記のコマンドを入力。
- (config)#capwap ap ip address 192.168.a.b 255.255.255.0
- (config)AP#capwap ap ip default-gateway 192.168.a.254
(最初ココで嵌った。設定が入ったままでインターフェースのIPアドレスだけ設定し直せば良いかと思ったけど、DHCPクライアントが停止しないため、DHCPがタイムアウトしたタイミングでBVI1のIPアドレスがリセットされてしまい、ファイル転送中に強制タイムアウトになってしまう。capwapの設定から一旦リセットし、手動でIPアドレス周りを再設定することで行けた感じ。)
- exitする。
- 念のため、APからtftpサーバーにPINGが通ることを確認する
- TFTPでファームウェアを転送。コマンドは↓
- archive download-sw /force-reload /overwrite tftp://192.168.a.c/ap3g2-k9w7-tar.153-3.JF12.tar
- 自動的に再起動すると、自律型として起動してくるはず。あとは自分の事情に合わせて設定して楽しみましょー。
以上。